おとぎ話の世界のような路地裏ってありますよね。
中世からの歴史のある大通り、
いびつに並んだ古い建物群、
活気のあるカフェや市場、
寂れた雰囲気の狭い脇道、
そして、そこに住んでいる人々。
今回は、旅先でみつけた路地の描き方のポイントとコツを解説します。
1. 路地裏で描くときのポイント

この画像の街並み素敵ですよね。
ここはフランス東部にある都市・ブザンソンの表通りです。
こんな難しい路地の絵を描くなんて
かなりの上級者じゃないと無理ですよね。
わかります。
これはかなり難しいと思います。
このまま描くなら。
風景を描くといえば、
自然の風景(山・川・海・草原・畑など)もあります。
路地裏スケッチは、建物や路地や車など人の営みがある事です。
もちろん、どちらも魅力がありますが…
今回は街並みを描くためのポイントをお伝えしますね。
ポイントその1「陰影」

路地裏スケッチで描くべきポイントは、
まずは路地裏ならではの「光と影」を表現すること。
また、路地裏には独特の光の入り方があります。
建物の間から差し込む光や、日陰になっている場所など、光の表現にも注力することが大切です。
路地裏スケッチで描くべきポイントその1は「陰影」です。
これを描くことで、より素敵なな路地裏の風景をスケッチすることができます。
ポイントその2「遠近感と省略」
ステキな路地裏を全部細かく描くとしたら‥
時間がいくらあっても足りません。
つまり、いくつかのポイントを押さえて描く必要があります。
それが「遠近感と省略」です。
建物が密集しているため、
遠近感を表現しやすいのです。
遠くの建物は省略したり、
着色の際に淡くすること、
ぼやかすことでも表現できます。
描きたいポイントがあるはずです。
それは古い建物や曲がりくねった路地なのか、
看板なのか、車や路面電車なのか、
街灯や電線、洗濯物など、
その場所で描こうと思ったポイントはしっかり描きしましょう。
その上で、全てを細かく正確に描く必要はありません。
特に現場で描くなら、時間も限られますよね。
魅力的なポイントを絞り、
その他は省略して遠近感に活用しましょう。
ポイントその3「人や動物」

住んでいる人は見慣れたもので、
毎日感動していたら大変ですよね。
旅で訪れる旅行者はただの路地にも感動します。
その絵の人は地元のひとなのか
旅行でおとずれたひとなのか…
遠くに猫が歩いていたり
空には鳥が飛んでいたり
絵の中に「生き物」がいるだけで
温かみがでたり、親近感だ沸いたり
時にはその絵の主人公になったりします。
路地裏スケッチでは「人や動物」をいれましょう。
ポイントその4「季節感」

春には、植木鉢に花が咲いていたり
夏には、人々が薄着だったり
秋には、落ち葉や木々が色づいたり
そして冬には、雪が積もっている。
どこに季節感をいれるのか、
ちょっと気にするだけで変わります。
ポイントその4は「季節感」を表現することです。
俳句でいうところの「季語」ですね。
路地裏スケッチの描き方

路地裏スケッチのポイントは押さえました。
つぎに描き方10ステップを紹介しますね。
旅先で素早く描くことにフォーカスします。
描き方10ステップ
路地裏スケッチでの構図の考え方については、以下のざっくりポイントがあります。
まずは縦書きにするのか、横書きにするのか決めなくてはなりません。
私は路地裏スケッチは縦書きすることが多いと思います。
両側に建物を描き、奥行きと高さを表現するためです。
街全景や街角を描く際は横書きが多いです。これは広さを出すためです。
ただ、どちらが正解ということはないので、主観で決めます。
路地裏スケッチは道路を描くことになります。
その道路は平らなのか、上り坂・下り坂なのかで描き方が変わります。
ここはまた図解を用いて解説しますね(リンク作成中)
路地裏をスケッチする場合は、道路を描くことになり奥行きが出ます。
自分の目線と奥行きの1番奥にある消失点を意識すると描きやすい・・
写真を見るとわかりやすいですが、そのまま描くと味気なくなったりします。
道があって両側に建物があるという構図でOKです。
建物があって道がある構図が決まったら、鉛筆で下書きします。
ざっくりで良いので、建物があって道があるのがわかる下書きをします。
下書きの建物の中でポイントになる部分を書き込んでいきます。
私は耐水性ペンを使うことが多いです。
素早く描きたいので、雰囲気が伝わればOKという気持ちで描きます。
路地裏には人々の生活が息づいています。
そのため、人物を描き込むことでスケッチにリアリティを与えることができます。
路地裏は日差しが差し込みにくい場所が多いため、光と影の表現が重要です。
建物や植物の影を上手く描くことで、スケッチに立体感を与えることができます。
光の当たっている明るい部分、影になっている暗い部分を描きます。
難しい言葉で言うと「グリザイユ技法」なんて言ったりもします(影だけ先に描く方法)
私は素早さにフォーカスしているので、これをコピックでやったりしています。
背景に空を入れるのかどうかです。
空の描き方でその時の時間帯がわかります。
お昼なのか、夕方なのか、天気もわかりますね。曇りなのか晴れてるのか。
一気にその場の雰囲気が出てくるでしょう。
水彩で色をつける場合は最初に塗ります。
水彩絵の具を混ぜて、素敵な色を作り、気持ち良く塗っていきます。
基本的には大きい場所から水を含ませて塗っていくのですが、水が乾く時間が必要になってきます。
色塗りは、絵の具の質によっても大きく変わりますので、良いものを選んでもいいと思います。
木の緑を上手く作れるようになるともはや玄人です。
ポイントになっている車や看板、ポストや街灯などをしっかり描きます。
濃い色をしっかりとのせると絵が引き締まります。
看板の文字など白抜きしたい箇所は、修正ペンを使うと早いです。
歩いている人は白抜きすると結構いい感じになります。
サインを入れたら完成です、ちょっとした画伯気分になれます。
以上のポイントを意識しながら路地裏スケッチを行うことで、より魅力的な作品を制作することができます。
最終的には一点透視図法〜三点透視図法などの構図を使うことになります。
ですが、これを説明するとかなり長くなってしまうので、また別の機会にご紹介しますね。
旅先で素早く描く、ちょっとハードルを下げて画伯気分になりましょう。
色使いのポイント
路地裏スケッチでの色使いのポイントは、自然な色合いを選ぶことです。
路地裏は、古い建物や石畳が多く、自然な色合いが多いため、派手な色を使うと違和感が生じます。
また、影や光の表現にも注意が必要です。
影は青みがかった色合いで表現し、光は黄色みがかった色合いで表現することで、よりリアルな表現ができます。
さらに、建物や街並みの雰囲気に合わせて、色のトーンを調整することも重要です。
例えば、古い街並みでは、ややくすんだ色合いが適しています。
一方、新しい街並みでは、鮮やかな色合いがよく似合います。
これらのポイントを意識して、路地裏スケッチを楽しんでみてください。
なぜか素敵に見えるテクニック
素敵に見えるのは絵が上手いからだけではありません。
素敵な場所に来ている自分が感動していると素敵に描けたりします。
また、スケッチブックや画材は小さいものがおすすめです。
路地裏は狭いですし、旅先では時間も限られています。
建物や路地の形状、影の表現、そして人物や植物の描き方を練習するとすぐに上達します。
特に人や車を描くテクニックを練習すると劇的に絵が素敵に見えると思います。
道具と場所を選ぶこと
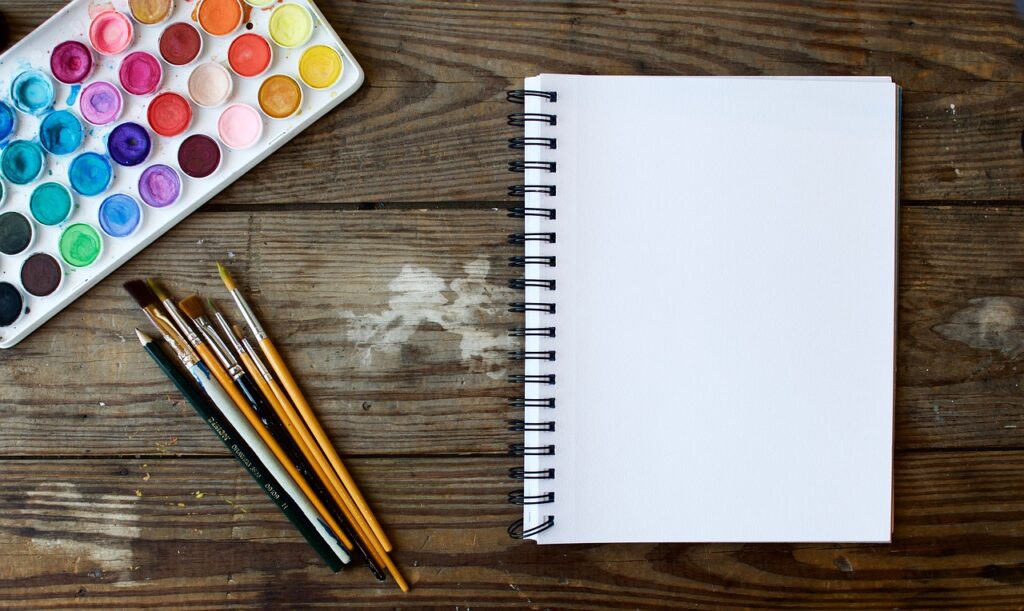
スケッチブックの使い方
路地裏スケッチでのスケッチブックの使い方についてご紹介します。
スケッチブックは、ページの大きさや紙質にこだわって選びましょう。
また、ページ数が多いものや、リング式のものなど、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
私はハガキサイズの画用紙(市販のもの)で描くことが多いです。
そのまま現地から送れることが最大の魅力で、不意に届いたらかなり喜ばれます。
また、スケッチブックには日付や場所、自分の感想などを書き込んでおくと、後で振り返るときに役立ちます。
ペンの選び方
スケッチ用具の選び方についてご紹介します。
まず、ペン先の太さを選ぶことが大切です。
建物や道路の細かい部分を描く必要があるため、細いペン先が適しています。
0.3〜0.5mm程度のペン先がおすすめです。
次に、インクの色を選ぶことが重要です。
古い建物や街並みを描くことが多いため、黒や茶色のインクが適しています。
また、水に強い防水インクを選ぶことで、雨の日でもスケッチを楽しむことができます。
海外風景スケッチの楽しみ方
路地裏スケッチは、都会の喧騒から離れ、静かな時間を過ごすことができる素晴らしい趣味です。
スケッチをすることで、周りの景色や建物の細部をよく観察することができます。
そのため、建物や風景に対する感性が磨かれ、自分自身のアイデアや感性が広がっていくことが期待できます。
スケッチはストレス解消にも効果的です。
都会の喧騒から離れ、自分自身のペースでスケッチを楽しむことで、心身ともにリフレッシュすることができます。
まとめ

旅先で路地を描いてみると
歩いているだけでは見過ごす小さな発見があります。
その絵で現地を紹介することにも繋がります。
現在のSNS社会ではその機会も多いはずです。
その影響力で「地球の裏側のひとがそこに行く理由」になったりもするのです。
路地裏スケッチの描き方のヒントとコツを押さえて、ぜひ挑戦してみてください。

